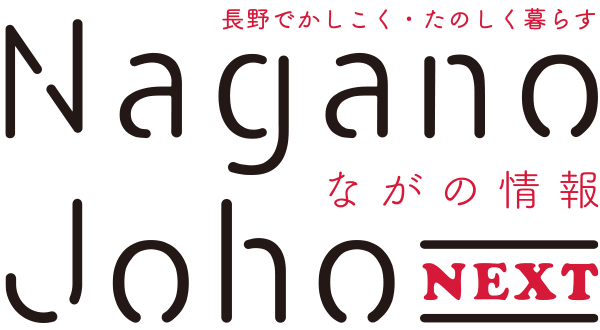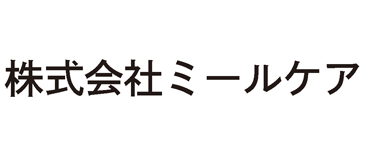-

誰もが笑顔になれる
安全・安心で美味しく
持続可能な社会に
貢献できる「食」を目指して。-
株式会社ミールケア
取締役副社長
関 友樹さん
-
株式会社ミールケア
-

2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年までに達成すべき世界共通の目標が示されてから、今年で10年。私たちは、持続可能な社会へと舵を切れているのでしょうか。
このシリーズでは、さまざまな課題解決のために、長野の企業や団体がどんな取り組みを始めているのかをご紹介します。今回は、株式会社ミールケアの取締役副社長、関友樹さんにお話を伺いました。
ただ作るだけではない
ミールケアの給食を届けたい。
 平成2(1990)年に創業し、今年35周年を迎えたミールケアは、「給食」のプロとして、安全・安心で美味しい給食を作り続けてきました。ご縁を大切に、ミールケアにしかできない給食の在り方を追求し続けることで、現在は長野・東京・大阪の3拠点を中心に、全国約580園以上もの保育園や幼稚園、認定こども園さんの給食に携わらせていただいています。ざっと計算すると、毎日約55、000食。私たちは、この1食1食を大切にすることで、子どもたちの笑顔と健康を守りたいと願っています。
平成2(1990)年に創業し、今年35周年を迎えたミールケアは、「給食」のプロとして、安全・安心で美味しい給食を作り続けてきました。ご縁を大切に、ミールケアにしかできない給食の在り方を追求し続けることで、現在は長野・東京・大阪の3拠点を中心に、全国約580園以上もの保育園や幼稚園、認定こども園さんの給食に携わらせていただいています。ざっと計算すると、毎日約55、000食。私たちは、この1食1食を大切にすることで、子どもたちの笑顔と健康を守りたいと願っています。
そのために取り組んでいるのが、「食育」です。ただ給食を作るのではなく、子どもたちが食材や栄養を楽しく学べるよう工夫し、年間を通してさまざまな活動を行っています。実際に食材に触れ、その背景を知ることで、今まで苦手だった野菜が食べられるようになった子どもたちも大勢います。親御さんからお礼を言われるたびに、食育を通してご家庭まで支援が届いているなと実感することができ、本当に嬉しく思っています。さらに、各地域の郷土食を給食に取り入れることで、地域に伝わる「食文化」の継承にも力を注いでいます。
またミールケアは、園の先生方や親御さんの声を聞くことで、常に進化し続けてきました。昆布と椎茸だけでとった「出汁」や、卵・乳不使用の「やさいぱん!」も、アレルギーのある子どもたちに、みんなと同じ給食を食べる喜びを感じてほしいという思いから開発したものです。
持続可能な「食」の在り方を
追求していきたい。
 こうした取り組みや経験は、「信州ビュッフェレストラン みーるマ~マ」や「ベーカリーショップ みーるマ~マ」にも展開されています。店舗がある穂保の地は、令和元(2019)年の台風19号による千曲川の決壊で、すべてが土砂に埋まりました。非常に辛く苦しい経験でしたが、私たちがこの地に戻ることで地域全体の復興に貢献できればと、社員全員で泥を掻きだし、多くの方のご協力を得て、令和4(2022)年12月に再オープンすることができました。また、時期を同じくして自社農園も拡大し、安全・安心な農業の基準となる「JGAP」や、障がいのある方とともに農業に取り組む「ノウフクJAS」を取得。環境に優しい持続可能な仕組み作りにも着手しました。
こうした取り組みや経験は、「信州ビュッフェレストラン みーるマ~マ」や「ベーカリーショップ みーるマ~マ」にも展開されています。店舗がある穂保の地は、令和元(2019)年の台風19号による千曲川の決壊で、すべてが土砂に埋まりました。非常に辛く苦しい経験でしたが、私たちがこの地に戻ることで地域全体の復興に貢献できればと、社員全員で泥を掻きだし、多くの方のご協力を得て、令和4(2022)年12月に再オープンすることができました。また、時期を同じくして自社農園も拡大し、安全・安心な農業の基準となる「JGAP」や、障がいのある方とともに農業に取り組む「ノウフクJAS」を取得。環境に優しい持続可能な仕組み作りにも着手しました。
ミールケア独自の「循環型システム」は、まず地元の農家さんや自社農園で採れた規格外野菜の活用から始まりました。栄養や美味しさは変わらないのに捨てられてしまうことが多い規格外の野菜を使ってメニューを開発し、「みーるマ~マ」で提供。食べ残しは捨てるのではなく、堆肥として活用できるようにしました。ミールケアでは、この堆肥箱を「宝箱」、「未来箱」と呼んで、作られた堆肥は自社農園の土づくりに活用しています。栄養たっぷりの土壌で育てられた美味しい野菜や果物は、安全・安心なメニューに生まれ変わり、「みーるマ~マ」を訪れるお客様をお迎えするのです。この、「作る、食べる、活かす」の、いのちの輪を循環させることで、地球にも人にも優しい未来を目指し、持続可能な社会の実現に少しでも寄与できればと思っています。優しい循環から生まれた美味しい「食」で、皆さんを笑顔にすることができればこんなに嬉しいことはありません。ぜひ一度、穂保の「み~るんヴィレッジ」にも遊びにきてください。